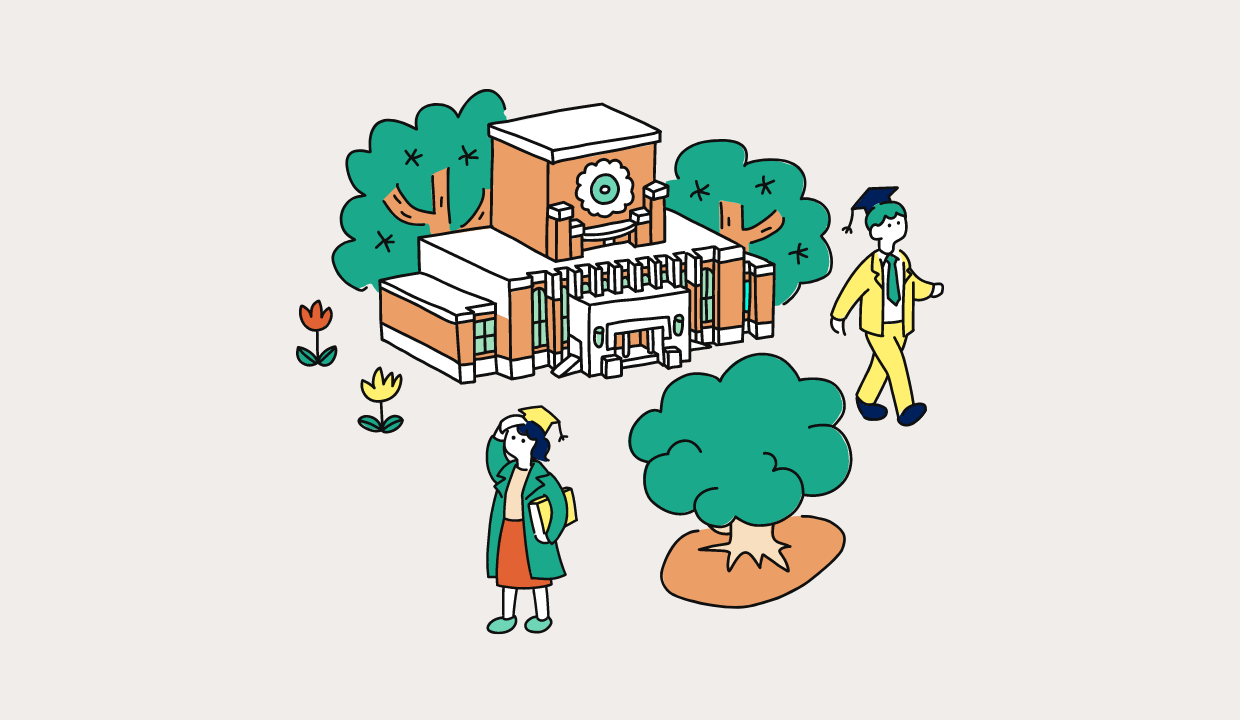西太平洋・アジア生物多様性研究ネットワーク(DIWPA)

DIWPA(西太平洋・アジア生物多様性研究ネットワーク、でゅーぱ)は、西太平洋・アジア地域を対象として1993年12月に発足したDIVERSITAS(生物多様性国際共同研究計画、2012年にFutureEarthに統合)に所属する生物多様性研究者の地域ネットワークであり、京都大学生態学研究センターが現在に至るまで事務局を運営しています。DIWPAには、令和7年3月末現在、世界37カ国の428名の研究者が登録しています。DIWPA事務局では、ニュースレターやウェブサイトなど、さまざまな媒体を通じてメンバーに情報を流すことによって地域の生物多様性研究の活性化を図るとともに、アジア地域の生物多様性研究をまとめた英文書籍3冊をシュプリンガーから発行しています。
DIWPAについて特筆すべきは、当該地域における若手研究者育成事業です。これは、国際公募により西太平洋やアジアから選抜された優秀な若手研究者を招へいし、水圏や森林などのさまざまな生態系において、気候変動、森林伐採、河川改修などの人為撹乱に伴う環境の改変が生態系の生物群集に及ぼす影響を把握するための長期生態系観測を行うワークショップを、コロナ時期を除いて毎年継続して開催しています(International Field Biology Course。以下、IFBCと略)。

IFBCは、京都大学理学部の陸水生態学実習と他大学を含む大学院生を対象とするワークショップとの同時開催で行っており、日本人学生と外国人研究者とが混じり合うようにグループを組むなど、若手研究者の英会話スキルアップなどを通じた人材育成にも工夫しています。ここ数年では、2023年8月20日から26日にかけて琵琶湖および沖島で開催したIFBC(写真1)ではタイの博士課程大学院生の参加者が、2024年12月9日~15に小笠原(父島)において開催されたIFBCではインドの博士課程大学院生とフィリピンの修士課程大学院生が、IFBCにて学びました。IFBCは、日本国内のその他では長野県木曽福島の木曽川集水域でも開催しているだけでなく、アジア諸国、たとえばタイ、インドネシア(写真2)、マレーシアなどでも開催実績があります。2025年度には、スリランカでの開催を予定しています。
さらに、JSPSのプログラムを活用した業績もあり、2022年度にはJSPSのBRIDGEプログラムにより、DIWPAメンバーであるインドネシア・BRIN・陸水学研究センターの主任研究員が当センターに滞在し、共同研究を行いました。加えて、タイのDIWPAメンバーとの国際連携研究活動として、タイ熱帯季節林に生育する281樹種の21の葉の生理形質に関するデータベースを作成、誰でも自由に使えるよう一般公開するとともに、その解析データは2023年に国際誌で発表されました。DIWPAの活動は、主に当該地域の発展途上国の若手研究者を対象としたキャパシティ・ビルディングとして、国内外から極めて高く評価されています。